マンション・住宅の防災準備|ハザードマップ & 必須防災グッズ
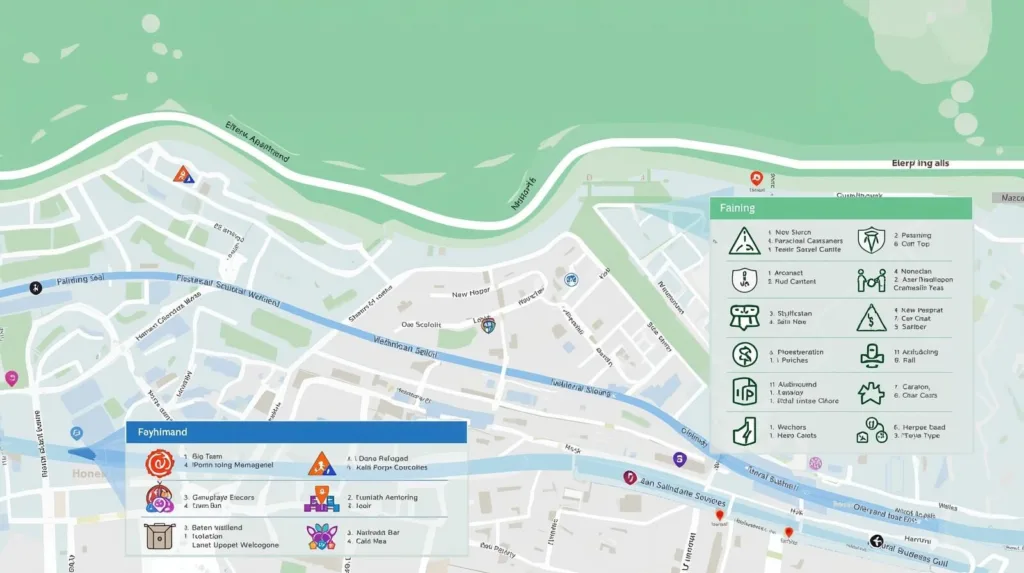
- マンション購入後すぐに始める防災対策の手順
- ハザードマップを活用した実践的なリスク把握方法
- 階層・構造別の災害リスクと対策の違い
- 効果的な防災グッズの選び方と配置方法
- マンション特有の避難・備蓄戦略
ハザードマップを「使う」

3ステップで確認する
「ハザードマップって見方がよくわからない」お客様から、本当によく聞く言葉です。
確かに色分けされた地図を眺めているだけでは、いまいちピンとこない。でも実は、ハザードマップは暮らしを守るための「取扱説明書」なんです。
不動産購入や賃貸契約の際に、宅建士から説明がある「重要事項説明」でも、ハザードマップについての説明が義務化されています。
私が宅建士資格を取得した際には、すでに義務化されていて、試験でも1問出題されました。
- 自分の住所を入力して「色」を確認: ハザードマップポータルサイトで、洪水・土砂災害・液状化・津波のリスクレベルをチェック。黄色は浸水の可能性あり、赤色は高リスク
- 避難所まで実際に歩いてみる: スマホの地図アプリだけでなく、実際に足で確認。段差や車椅子で通れない場所も把握
- 「もしも」の連絡ルールを決める: スマホが使えない場合を想定。「家が安全なら家から出ない」「家がダメなら〇〇学校に集合」など具体的に
階層別の災害リスク
一戸建てとマンションでは、災害時に注意すべきポイントが全く違います。
内閣府防災情報でも指摘されているように、高層建築物では階層別の対策が欠かせません。
| 階層 | 主なリスク | 重点対策 | 備蓄のポイント |
|---|---|---|---|
| 低層階(1-3F) | 浸水、津波、液状化 | 垂直避難の準備 | 上階への移動を想定 |
| 中層階(4-10F) | 停電時エレベーター停止 | 階段利用の体力確保 | バランス型備蓄 |
| 高層階(11F以上) | 強風、長時間孤立 | 停電や断水による長期間の自宅待機 | 多めの備蓄が必要 |
防災グッズの揃え方と配置

「引っ越しの延長」で揃える
「防災グッズって何から揃えればいいの?」
新居に入居された方から、本当にたまに受ける質問です。
おすすめは「引っ越しで買うものの延長」として考えること。
特別な防災グッズではなく、普段使いできるものを中心に選ぶと、無駄がありません。
政府広報オンラインの推奨品目をベースに、マンション特有の制約を考慮したリストを作りました。
以下は、私が実際にホームセンターやネットショップで調査した価格をもとにした概算です。
店舗や時期によって変動しますが、目安として参考にしてください。
| カテゴリー | 具体的な内容 | 目安予算(概算) |
|---|---|---|
| 飲料水 | 1人1日3リットル×3日分(2Lペットボトル5本程度) | 約1,500円 |
| 非常食 | レトルトカレー・パックご飯・缶詰・カロリーメイト | 約3,000円 |
| 照明・電源 | LEDランタン・単三電池・モバイルバッテリー | 約5,000円 |
| 衛生用品 | 簡易トイレ10回分・除菌ウェット・マスク | 約2,000円 |
| 防寒・雨具 | アルミブランケット・レインポンチョ | 約1,500円 |
| 情報収集 | 手回し充電ラジオ・緊急連絡先リスト・現金2万円 | 約2,000円 |
| 合計 | 約15,000円 |
実は、これらの多くは楽天の防災セットなどでまとめて購入できます。
バラバラに買うより効率的で、見た目もスッキリ。
私も最初はバラバラに買っていましたが、途中からセットに切り替えました。
配置場所を決める
私の知り合いのお宅で、防災準備がしっかりしている方がいます。
その方は、「使う場面を想像して配置」していました。
- 玄関: すぐに持ち出せる1dayセット(リュック1つ、重さ5kg以内)
- 寝室: 夜間災害用の懐中電灯・スリッパ・ホイッスル
- キッチン: 食料・水の主力備蓄(ローリングストック活用)
- リビング: 家族共用のラジオ・充電器・救急箱
- バルコニー: 給水用ポリタンク・簡易トイレ(臭気対策)
マンション特有の対策
管理組合との連携
マンションの大きなメリットは、「共助(お互いに助け合う)」の仕組みを作りやすいこと。
気象庁の緊急地震速報の利活用状況等に関する調査でも、マンションの緊急放送や表示によって緊急地震速報を見聞きしたという調査があります。
- 非常用電源: 停電時に最低限動く設備(共用部照明・1基のエレベーター)
- 受水槽容量: 断水時に各戸で使える水量(通常1日分程度)
- 防災倉庫: 共用備蓄品の内容と利用ルール
- 避難設備: 避難はしご・救助袋の設置場所と使用方法
- 通信手段: 携帯電話不通時の連絡方法(館内放送等)
エレベーター停止への備え
マンション特有の災害リスクで最も現実的なのが「エレベーター停止」。
消防庁のエレベーター利用避難に関する国内外の事例の調査研究でも、この問題は取り上げられています。
私が不動産業界で聞いた話では、災害直後のエレベーターの復旧には数日から1週間程度かかることもあるそうです。
階数が高いほど、階段での移動が困難になります。
| 階数 | 対応可能性 | 推奨対策 |
|---|---|---|
| 3階以下 | 階段利用でも対応可能 | 定期的な外出OK |
| 4-8階 | 1日数回の階段利用が限界 | 必要な買い物は最小限に |
| 9-15階 | 必要最小限の移動のみ現実的 | 備蓄を多めに準備 |
| 16階以上 | 基本的に室内待機 | 1週間分の備蓄必須 |
在宅避難か避難所か
高層階で地震などはかなり揺れるため心配になりますが、実はマンションは構造的に安全性が高いんです。
多くの場合「在宅避難」が推奨されます。
ただし、状況によっては早めに避難所への移動が必要になることも。
- 建物に目立った損傷がない(ひび割れ・傾き等なし)
- 水道・ガス・電気のいずれか1つ以上が機能している
- 3日分以上の備蓄がある
- 持病の薬が十分にある
- 近隣住民との連絡が取れている
- 建物に構造的な不安がある
- 火災やガス漏れの危険性がある
- ライフライン全停止が1週間以上続く見込み
- 医療的なケアが必要
- 近隣との連絡が完全に途絶えている
継続的な備え
季節の行事と組み合わせる

防災対策で意外と見落とされがちなのが「メンテナンス」。
せっかく準備した防災グッズが、いざという時に使えなければ意味がありません。
内閣府の防災教育ページでも、継続的な取り組みの重要性に関するページがいくつかあります。
でも「毎月チェック」なんて負担に感じますよね。
そこでおすすめなのが、季節の行事と組み合わせる方法です。
私の家では、年2回の衣替えの時期に一緒に必ず確認するようにしています。
| 時期 | チェック内容 |
|---|---|
| 年末の大掃除(12月) | 全体的な見直し・家族構成変化の反映 |
| 新年度準備(3月) | 連絡先・避難所情報を更新 |
| 梅雨前(5月) | 水害対策・雨具を点検 |
| 防災の日(9月) | 備蓄食品の入れ替え・機器動作チェック |
防災の日(毎年9/1)は、備蓄していた非常食を入れ替えもかねて、家族みんなで食べるようにしています。
これが意外と楽しいんですよ。
「今年の非常食はどんな味だろう?」って、子供たちも楽しみにしています。
スマホアプリの活用
現代の防災対策では、デジタル技術をうまく活用することで、より効果的な備えができます。
気象庁の防災情報をはじめ、公的機関のアプリも充実してきました。
ただし、「アプリ頼みになりすぎない」ことも大切。
災害時にはスマホの電池切れや回線混雑が起こるためです。
私も東日本大震災の時、スマホが全く使えなくて困った経験があります。
| アプリ名 | 主な機能 | オフライン対応 |
|---|---|---|
| Yahoo!防災速報 | 緊急速報・避難情報 | 一部対応 |
| NHKニュース・防災 | 災害情報・ライブ映像 | × |
| 特務機関NERV防災 | 気象警報・地震情報 | ○ |
| ハザードマップポータル | 各種ハザードマップ | ○ |
| 災害用伝言板 | 安否確認 | ○ |
まとめ:小さな備えが、大きな安心を生む
事前の備えがある家庭とない家庭では、災害後の回復スピードが圧倒的に違う。
これは、私が不動産業界で何度も見てきた現実です。
- 家族の不安が軽減: 「準備してある」という安心感で日常も穏やか
- 災害時に冷静な判断: パニックにならず、適切な行動が取れる
- 住まいの資産価値を守る: 迅速な対応で被害を最小限に抑制
- 近隣とのつながり: 共助体制で地域全体が安全に
- 復旧が早い: 備えがあることで、元の生活への復帰が早くなる
「防災対策」というと身構えてしまいがちですが、実は「安心できる暮らしを作ること」と同じ。
新しいカーテンや照明を選ぶのと同じような感覚で、防災グッズも暮らしの一部として取り入れてみてください。
今日からできることは、まずハザードマップポータルサイトでお住まいの地域をチェックすること。
そして週末に、家族で防災グッズを見に行ってみること。
この小さな一歩が、あなたとご家族の大きな安心につながります。
災害は「いつか来るもの」ではなく、「今日来るかもしれないもの」。
でも、適切な備えがあれば、必要以上に恐れることはありません。安心できる毎日のために、今できることから始めてみませんか?






